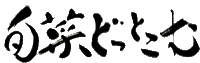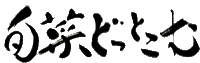|
氷上郡青垣町−宮井さんちの田んぼの稲刈り・畑見学
 今日は、氷上郡青垣町の宮井さんの田んぼに稲刈りに行きます。本当は先週が刈り取りだったのですが、以前お聞きしていたのが5日だったので、この日しか都合がつきません・・・、と大変ご無理を申し上げたのでした。いつものことながら旬菜の勝手をおききくださいまして、なんと稲を一筋刈り取らずに残して下さっていたのです。ほんとにすみません。 今日は、氷上郡青垣町の宮井さんの田んぼに稲刈りに行きます。本当は先週が刈り取りだったのですが、以前お聞きしていたのが5日だったので、この日しか都合がつきません・・・、と大変ご無理を申し上げたのでした。いつものことながら旬菜の勝手をおききくださいまして、なんと稲を一筋刈り取らずに残して下さっていたのです。ほんとにすみません。
さて、その残していただいた1週間の間に、いのししさんが出没し、お味見をしていかれたそうです。稲が場所によって倒れていたり、稲穂が落ちていたり、いのしし出没の形跡が残っていました。宮井さん、重ねて申し訳ございませんでした。
さて今回、旬菜メンバーは女性のみ4人の参加です。男手は丹波食の会の宇津江さんのご主人と宮井さんのお二人です。作業は、稲を手刈りし、それを束ね、稲木にかけるまでです。はて、さて、大丈夫かな。昼食のおにぎり目指してがんばろう!
 はじめに、宮井さんから作業手順や注意事項を教えていただきました。稲の株をしっかりにぎり、鎌はスナップを効かせて手前に引きます。1株づつ刈り取り、女性の手の大きさでは2〜3株までを一束にして畦に置きます。その束の上にもう一束をV字になるように、根元を重ねて二束で1セットにして置いていきます。後でこの二束を縄で結わいて稲木にかけていくのです。 はじめに、宮井さんから作業手順や注意事項を教えていただきました。稲の株をしっかりにぎり、鎌はスナップを効かせて手前に引きます。1株づつ刈り取り、女性の手の大きさでは2〜3株までを一束にして畦に置きます。その束の上にもう一束をV字になるように、根元を重ねて二束で1セットにして置いていきます。後でこの二束を縄で結わいて稲木にかけていくのです。
稲刈りは近くで作業をすると危ないので、間をあけて4人が離れて稲穂の列に入ります。1週間の間に稲穂が乾燥してきているので、重量が軽くなっていて女性でも思ったよりは手早く刈り取れそうです。はじめこそ、鎌の使い方に手間取りましたが、すぐに調子をつかんで皆もくもくと刈り取っていきます。




途中、宮井さんが「あまり必死にならずにおしゃべりしながらのんびりおやりください。たまには伸びをして、腰を伸ばしたほうがいいですよ。」と声をかけてくださいました。「は〜い!」と旬菜メンバー。
 思いのほかテンポよく刈り取りが終わり、V字に並んだ稲の束を前にして、宮井さんがわらで稲を束ねる手順をご指導くださいました。5本ほどのわらを両手に持ち、稲の二束が重なった根元の部分にあて、一周させます。出会ったわらを二度ほどねじって、一方を一周したわらに挟み込みます。宮井さんの手をみているととても簡単そうです。 思いのほかテンポよく刈り取りが終わり、V字に並んだ稲の束を前にして、宮井さんがわらで稲を束ねる手順をご指導くださいました。5本ほどのわらを両手に持ち、稲の二束が重なった根元の部分にあて、一周させます。出会ったわらを二度ほどねじって、一方を一周したわらに挟み込みます。宮井さんの手をみているととても簡単そうです。
 これが、実際してみると思うようにいきません。結わいたはずの束から稲が外れてきます。これでは稲木にかかりませんね。もう一度やり直し!しっかり結わいておきましょう。 これが、実際してみると思うようにいきません。結わいたはずの束から稲が外れてきます。これでは稲木にかかりませんね。もう一度やり直し!しっかり結わいておきましょう。
宇津江さんと他3人が稲を結わいて稲木にかけている間に、お昼の準備をすべくメンバーの1人が畦でおにぎりをにぎり始めました。もうすぐごはんだ、がんばろう!
落穂拾い。田んぼの稲刈りが終わったあと、落ちている稲穂を拾う作業です。これが、あの落穂拾いなんだ、とお恥ずかしながらはじめて理解したのは私ひとりでしょうか。地面を見ながら歩いていても、はじめはあまり目に付きません。ところが、徐々に目が慣れてくるとあちらにもこちらにも、ああもったいない、いっぱい落ちているのがわかります。そこそこ拾って、稲刈り一連の作業は終了!
 今日のおにぎりのお米は、先週刈り取った宮井さんちの自然農法でつくったお米です。味比べにと、宇津江さんがスーパーで高級こしひかりを買ってこられ、こちらもおにぎりになっています。さあ、勝負。 今日のおにぎりのお米は、先週刈り取った宮井さんちの自然農法でつくったお米です。味比べにと、宇津江さんがスーパーで高級こしひかりを買ってこられ、こちらもおにぎりになっています。さあ、勝負。
 高級こしひかりは柔らかく甘味があります。宮井さんちのお米は噛み応えのある味わい深い元気米です。稲刈りを終えた私たちには、この田んぼでできた宮井さんちのお米のほうが、とびきりおいしく感じられました。 高級こしひかりは柔らかく甘味があります。宮井さんちのお米は噛み応えのある味わい深い元気米です。稲刈りを終えた私たちには、この田んぼでできた宮井さんちのお米のほうが、とびきりおいしく感じられました。
そのうえ、宮井さんお手製の梅干がまたなんとも美味!高菜(こちらでは、かっぱ菜と呼ぶそうです)の漬物や煮びたし、宇津江さんの奥様お手製の野菜の煮物。田んぼで豪華なおにぎりパーティーです。
旬菜での田舎めぐりは、いつもおいしい食べ物が真ん中にあるのがいいのです。
 腹ごしらえが終わったら、今度は宮井さんちの畑に行きます。田んぼの向かい側には、前回もいただいた白なすと甘長。少し離れた畑には、先ほどご馳走になった高菜や春菊ができています。自然農法で作っておられるので、草も一緒にはえています。田んぼも畑も宮井さんお一人でされているので、草取りも大変です。宮井さんはいつもおっしゃいます。「お天とさまと水と土の中の微生物くんが作物を作ってくれるのです。わたしはお手伝いをしているだけです。」頭が下がります。 腹ごしらえが終わったら、今度は宮井さんちの畑に行きます。田んぼの向かい側には、前回もいただいた白なすと甘長。少し離れた畑には、先ほどご馳走になった高菜や春菊ができています。自然農法で作っておられるので、草も一緒にはえています。田んぼも畑も宮井さんお一人でされているので、草取りも大変です。宮井さんはいつもおっしゃいます。「お天とさまと水と土の中の微生物くんが作物を作ってくれるのです。わたしはお手伝いをしているだけです。」頭が下がります。
 近くにある栗の木には、大きな丹波栗が実っています。 近くにある栗の木には、大きな丹波栗が実っています。
 秋ですね。今日も旬菜「かっとびけいこ号」の車の後部荷台には、おみやげの秋の実りがいっぱいです。稲の手刈り初体験の旅は、これでお・わ・り。 秋ですね。今日も旬菜「かっとびけいこ号」の車の後部荷台には、おみやげの秋の実りがいっぱいです。稲の手刈り初体験の旅は、これでお・わ・り。
<<文章:桃田 直子>>
▲ページTOPへ
レポート一覧へ戻る
|