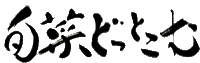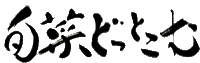|
Ⅰ[今回はツアーガイドさん付きだぞ!]
長い梅雨が明けたと思ったら、秋のような涼しい毎日でしたが、この日は夏の青空が広がるとてもすがすがしい朝でした。初参加の方々との挨拶もそこそこに「かっとびけいこ号」に乗り込み出発です。待ち合わせ場所に到着したころには、太陽の光が容赦なく照りつける真夏日となっていました。
ここで、宇津江さんより今日の日程表を受け取りました。はじめに青垣町に行き、丹波少年自然の家を見学。その後、名水銚子ケ水を汲み、それから宮井さんの畑を見学。高源寺拝観後、高源寺そばで昼食。午後は、婦木さんのとうもろこし畑でとうもろこし狩りをした後に、柚津区で行なわれているイベント「ひまわり迷路」に挑戦。そこからシフトアップかすがの小橋さん宅を訪問し、宇津江さんのお宅に向かう途中、堤さんの畑の見学。なかなか中身が濃い内容です。
Ⅱ[青垣町訪問]
青垣町の丹波少年自然の家では、少年野球のチームらしき団体が合宿で来ているようです。ロッジやキャンプ場などでは、家族連れが飯盒炊さんの準備をしています。広々とした敷地の中にいろいろな施設が備わっています。木漏れ日のなかに立つと、ひんやりとした涼しい風が心地よく、美味しい空気をいっぱい吸い込みます。
 つぎに、一休和尚が見つけたという銚子ケ水を汲みにいきました。勢いよく流れ出る水を飲んでみると、味やくせがなく、さらっとした軟水という感じです。 つぎに、一休和尚が見つけたという銚子ケ水を汲みにいきました。勢いよく流れ出る水を飲んでみると、味やくせがなく、さらっとした軟水という感じです。
 「これで氷をつくってウイスキーを飲んだら、最高です」とは宇津江さんのご主人のお言葉。その言葉に喜ぶ旬菜ほかのメンバーです。 「これで氷をつくってウイスキーを飲んだら、最高です」とは宇津江さんのご主人のお言葉。その言葉に喜ぶ旬菜ほかのメンバーです。
Ⅲ[宮井さんの田んぼと畑]
次に伺うのは、宮井さんの田んぼと畑です。宮井さんは自然農法でお米や野菜をつくっておられます。以前、3月に雪降る中お邪魔したとき、畑の大根が凍っていたのが思い出されます。その時お約束した田植えのお手伝いはできませんでしたが、今度はぜひ夏に伺いたいという夢は果たせました。
 今回見学させていただいた田んぼは以前訪れた場所とは違いました。稲が青々と伸び、素人目には、先日までの長雨の影響はないように見受けられます。 今回見学させていただいた田んぼは以前訪れた場所とは違いました。稲が青々と伸び、素人目には、先日までの長雨の影響はないように見受けられます。
宮井さんにお話を伺います。
「雨が多かったので、つい先ごろまでは稲の生育が思わしくなかったですが、梅雨が明け10日ほどで随分良くなりました。でも、緑が薄く黄緑色のところは、雑草のほうが勝っているところで生育がよくありません。私が勘違いをして草刈が遅れたところもあります。と思えば、手を加えて助けてあげたつもりでも、手を加えないところのほうがよく生育することもあって、本当に難しいです」
「稲は、分蕨(ぶんけつ)が十分できる環境にすることが大事です。田植えの時、稲と稲の間隔をどれくらいにするかもその点では重要です。間隔が広いほうが稲が分蕨するには好ましいのですが、植える本数が少なくなります。全体の収穫量を考えると多く植えるほうがいいように思われます。ただ、分蕨が十分された稲は実りが多いので、1本の収穫量は多くなります。結局どちらがいいかは、一概に言えません。ただ、自分の力で充分に栄養を取り込み分蕨した稲の味は最高です」
「今年は人手が少ないので、除草が大変です。そこで、麻布を細長く反物状にした布マルチ風のものを畦や田んぼの稲の間に敷いて見ました。タイミング良く敷いたものは、除草の効果が充分あったようです。畦にも麻布を敷きたいのですが、その土地の持ち主の了解がもらえないとできません。このようなものを敷くと、土が柔らかくなって崩れやすくなるためで、除草できてもいいことばかりではないのです」
「今年は、気温が上がっていないので、水の温度が足りません。今ごろなら田んぼの水を触ったら熱くなっていないといけないのですが、まだぬるい程度です。今年は10月の第1週くらいに刈り取りを予定しています」
まだまだ、いろいろとお話を伺いたいのですが、今日は予定が詰っています。田植えはできませんでしたが、稲の刈り取りの助っ人として、ぜひお手伝いにきましょう!
畑には、白い肌をしたシルクなすや枝豆が植わっていました。帰りがけに、そのシルクなすと甘長を用意してくださっていました。甘長をその場でがぶりっと食べてみました。なんとおいしい味でしょう!真夏の香りがします。宮井さんありがとうございました。
Ⅳ[高源寺拝観と高源寺そば]
 高源寺は秋、楓の名所として有名なお寺です。その時期には観光バスがたくさんの人を運んでくるそうですが、この日は、我々以外には人の姿がありません。ただ一匹のねこが門前でのんびり座っているだけです。皆で写真を撮ろうと並んでいると、そのねこがのろりのろりと皆の前、中央位置にポーズをとるかのようにやってきました。これはただものではありませんぞ。 高源寺は秋、楓の名所として有名なお寺です。その時期には観光バスがたくさんの人を運んでくるそうですが、この日は、我々以外には人の姿がありません。ただ一匹のねこが門前でのんびり座っているだけです。皆で写真を撮ろうと並んでいると、そのねこがのろりのろりと皆の前、中央位置にポーズをとるかのようにやってきました。これはただものではありませんぞ。
高源寺の苔むした石段をゆっくり登っていると、時の流れがいつもと違って感じられます。ゆっくり、ゆったりした空間の中に溶け込んでいくようです。
のんびりと境内を散策し、俳句でも一句、ひねりたいところですが、やはりおいしい食べ物のほうが旬菜にはぴったりでしょうか。
 高源寺の入り口すぐのところに、高源寺そばがあります。ここのおそばやさんでは、宮井さんの畑で以前お目にかかった陶芸家の藤井さんがそば打ちをしていると聞いています。 高源寺の入り口すぐのところに、高源寺そばがあります。ここのおそばやさんでは、宮井さんの畑で以前お目にかかった陶芸家の藤井さんがそば打ちをしていると聞いています。
さっそく皆でざるそばの大盛りを注文。特産のあざみ菜の漬物もお願いしました。このあざみな菜は春日町の地場野菜でからし菜の一種だそうです。日本あざみ菜と高菜、からし菜、野沢菜を掛け合わせたもので、各々の特徴を引き出した漬物は、青垣町の名産品として道の駅でも好評だそうです。ぴりっと辛味があり地場の生酒がそれはそれはすすむそうです。
大盛りのおそばをぺろりとたいらげた皆さん。午後は婦木さんちのとうもろこし狩りではじまります。さあ行くぞ!
Ⅴ[婦木さんちの畑でとうもろこし狩り]
 婦木さんちのとうもろこし畑は、大忙しです。午前と午後、ともに団体さんがとうもろこし狩りにやってきます。その合間をぬって、旬菜グループ6人はとうもろこし狩りをするのです。申し訳のないような思いにかられながら、でもやるとなったらとことんやる旬菜メンバーです。いざ出陣。 婦木さんちのとうもろこし畑は、大忙しです。午前と午後、ともに団体さんがとうもろこし狩りにやってきます。その合間をぬって、旬菜グループ6人はとうもろこし狩りをするのです。申し訳のないような思いにかられながら、でもやるとなったらとことんやる旬菜メンバーです。いざ出陣。
前回訪れた畑とは別の畑にとうもろこしがありました。脇には、枝豆も実っています。背丈より高く伸びたとうもろこし畑に入ります。今回とうもろこしが実っているところをはじめて見ました。茎の比較的下のほうから枝が分かれるようにぬっととうもろこしが出ています。手で触ってみたときに、柔らかいものはまだ実が熟してしないそうです。しっかりした感じになったものが食べごろです。一人6本まで。吟味して、吟味して選びましょう。
 とうもろこしには種類がいろいろあるそうです。牛の餌用のものもあるそうです。とうもろこしは、違う種類の花粉でも受粉しやすいので、とても注意が必要だそうです。 とうもろこしには種類がいろいろあるそうです。牛の餌用のものもあるそうです。とうもろこしは、違う種類の花粉でも受粉しやすいので、とても注意が必要だそうです。
とうもろこしを選び終わると、今度は枝豆の収穫をさせていただきました。実のつきがよさそうな枝豆の茎を、元からばっさり切るのです。こちらは2株づついただきました。
となりの広場では、婦木さんの畑でできたもぎたてのトマトやきゅうり、そのほかの特産品が並べられています。氷水で冷やされたトマトときゅうりをがぶりっといただき、婦木さん手づくりの麦茶も2袋買いました。旬の新鮮な野菜をみたら、そのまま帰るわけにはいきません。おみやげいっぱい買いましょう。
Ⅵ[ひまわり迷路に挑戦]
 ひまわり迷路は、田舎TVで種まきの様子を放映していました。そのときは、どんな迷路になるだろうと思ってみていたのに、今回実際に挑戦することができるとは、驚きです。りっぱに育ったひまわりは背丈よりはるかに高く、行き先以外はかなり視界が遮られ、迷路にはぴったり。夏の日差しの中、ひまわりの大きな花に囲まれて、ひまわり迷路のスタンプラリーです。あちらにいったり、こちらにいったり。このときばかりは、暑かったです。 ひまわり迷路は、田舎TVで種まきの様子を放映していました。そのときは、どんな迷路になるだろうと思ってみていたのに、今回実際に挑戦することができるとは、驚きです。りっぱに育ったひまわりは背丈よりはるかに高く、行き先以外はかなり視界が遮られ、迷路にはぴったり。夏の日差しの中、ひまわりの大きな花に囲まれて、ひまわり迷路のスタンプラリーです。あちらにいったり、こちらにいったり。このときばかりは、暑かったです。
出口では、景品の交換や、新鮮な卵や野菜、木製の特産品の販売もありました。宇津江さんの奥様が山椒の木のすりこ木を買っていました。掘り出し物ですよ。
Ⅶ[小橋さん宅訪問]
さて、小橋さんといえば、シフトアップかすがというグループで田舎TVをインターネットで流している方です。この田舎TVがおもしろいのです。田舎のくらしをそのままビデオに撮り、そのまま流しているコーナーがあります。春日町の様子を知りたいとき、結構いいのです。田んぼの様子を毎日同じアングルから写真にとってカレンダーのようにしているコーナーもあります。稲の成長の様子を見ることができて、田んぼが身近に思えてちょっと気持ちが潤います。そんなおもしろTVを作り出している小橋さんとのお話は、旬菜ほかのメンバーにとっても収穫が見込めます。
田舎のそのままを知らせよう。そのために、いろんな人にお話を聞いたり、それを文章にしてもらったりする。そうすることで、自分たちが当たり前と思っていたことを認識し直すきっかけにもなる。ITを使って、だれもが書き込みのできる形式に改良していけば、消えてしまいそうな田舎のいいところ情報をどんどん掘り起こすことができる。四季折々の行事など暮らしのなかの文化を大事にしていきたい。と、話は広がります。
11月に予定している里山ウォーキングでは、地域通貨を購入してもらい、中山区の農家を自由に散策してもらう内容にしたいと考えているそうです。農家側には、たいそうにもてなすのではなく、ちょっと友人を招く程度まででお願いしているとのことです。
旬菜ほかのメンバーも思いを語りました。
生産者との交流でお客様としてのおもてなしを受けるということは、対等でない関係になってしまう。もっと人と人としてつながることが大事ではないか。また、地元で取れた旬の野菜をシンプルにおいしく料理する。その料理を気のきいた器に盛って、お話しながらゆっくり時間をかけて食べる。そこで人と人とがつながる。
また、たとえば神戸や大阪から車で2時間ほどでこんなステキな田舎に来ることができるということ、結構気軽に来ることができるということをもっと知らせる必要があるのではないか、など、人と人をつなぐコーディネイターの役割がやはり重要といえるでしょう。
この場にいる人がみな自分の関心のある分野に結び付けて語ります。いろいろな視点から都会と田舎を語ります。このような人の交流が、新しい活力を生み出すのでしょう。
時間の経つのも忘れ、里山ウォーキングに参加するぞ!と気持ちも新たに小橋家を失礼します。ここでも、おいしいお土産をいただきました。小橋さんのお母様お手製、うりの粕漬けです。お邪魔したうえに、ほんとうにありがとうございました。ごちそうになります。
Ⅷ[堤さんの畑、宇津江さんちで宴会]
 宇津江さんちのちょっと手前に、堤さんのお宅と畑、田んぼがあります。堤さんは脱サラをして、ご家族で春日町に引っ越してこられました。宮井さんと同じく、自然農法でお米やお野菜をつくっておられます。 宇津江さんちのちょっと手前に、堤さんのお宅と畑、田んぼがあります。堤さんは脱サラをして、ご家族で春日町に引っ越してこられました。宮井さんと同じく、自然農法でお米やお野菜をつくっておられます。
今年はとうもろこしに挑戦したそうで、2ケ所に植わっていました。うち1ケ所は草のほうが勝ってしまい、とうもろこしは不出来だそうです。また、細長い敷地にとうもろこしを植え付けたため、受粉がうまくいかなかったそうです。なるべく四角形の敷地に植え付けたほうが受粉のチャンスが増えてよいそうです。
 堤さんは合鴨農法で稲をつくっています。田んぼの稲は、宮井さんの田んぼの稲より少し若いようすです。稲の間から、合鴨が顔を出しました。と思ったら、いっせいに運動会みたくあちらからこちらへ向かって、ガアガア泳いできます。今度はUターンして、こちらからあちらへ、ガアガア泳いでいきます。元気だぞ。 堤さんは合鴨農法で稲をつくっています。田んぼの稲は、宮井さんの田んぼの稲より少し若いようすです。稲の間から、合鴨が顔を出しました。と思ったら、いっせいに運動会みたくあちらからこちらへ向かって、ガアガア泳いできます。今度はUターンして、こちらからあちらへ、ガアガア泳いでいきます。元気だぞ。
以前、淡路島五色町で出会った合鴨は生まれて10日ほどで小さかったですが、今日の合鴨は随分成長しています。雄雌が見分けられるほど、羽の色に違いがでています。合鴨たちは、稲が実りだしたら田んぼから引き上げるそうです。
堤さんもお土産をご用意してくださっていました。ぽちぽちのいぼがしっかりついている表皮のやわらかいきゅうりです。こんなにたくさんいただいて、すみません。ごちそうさまです。
宇津江さんちに到着します。今日はほんとに中身の濃い1日でした。宇津江さんご夫妻のガイドあっての内容です。ありがとうございました。
お庭のテーブルで、今回はお休みのため伺えなかったドイツ料理店のオードブルのハムをいただきながら、岩尾さん差し入れのドイツビールで疲れをとりましょう。今日一日で味わったステキな出来事や出会いを肴に、これからの夢をまたまた膨らませて、さらに実現に向けて、かんぱーい!
<<文章:桃田 直子>>
▲ページTOPへ
レポート一覧へ戻る
|