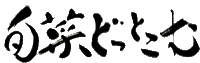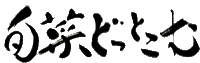|
婦木農園訪問
[春日町へ]
天気予報は雨。確かに空はどす黒く、今にもザァーと勢いよく降りだしそうな気配。われら3人は、「かっとびけいこ号」に乗り、春日町を目指します。
これまで行きたくても、なかなか行けなかった春日町の婦木さんの畑。今回も平日のため、旬菜メンバー全員で行くことは叶いませんでした。そんななか、英語堪能の強い味方がお一人参加してくれました。というのも、今日は春日町の宇津江さん宅に有機栽培農家を見学したいと、アメリカから学生さんが来ているのです。いろいろお話を聞きたいぞ。ついに旬菜の活動も国際的になってきた?!
宇津江さんちに到着すると、まずはアメリカから来た学生さん、ギデオンくんとご挨拶。ちょうど丹波新聞の取材を受けていたところです。彼のお家は、バーモント州でオーガニックのお店をしておられるそうです。雄大な自然に囲まれたふるさとのお写真を見せてもらいながらのお話や、日本でこれまでまわってきた山形と長野の交流の様子も教えていただきました。さて、ひととおり話が終わると、さっそく畑に向けて出発です。
[婦木さんの畑へ]
 婦木さんは、作業場で産消提携のグループ「あしの会」の会員向けに野菜を箱詰めしているところでした。つやつやとした元気な野菜が箱の中に並んでいます。今日は、野菜の種類が多くて、箱がいっぱいです。なす、きゅうり、キャベツ、ズッキーニ、万願寺とうがらし、じゃがいも、たまねぎ、かぼちゃ、青ねぎ、大葉、三度豆、ピーマン、えだまめ、トマトなど。 婦木さんは、作業場で産消提携のグループ「あしの会」の会員向けに野菜を箱詰めしているところでした。つやつやとした元気な野菜が箱の中に並んでいます。今日は、野菜の種類が多くて、箱がいっぱいです。なす、きゅうり、キャベツ、ズッキーニ、万願寺とうがらし、じゃがいも、たまねぎ、かぼちゃ、青ねぎ、大葉、三度豆、ピーマン、えだまめ、トマトなど。
 「今日はこんなにたくさんのお野菜が入れられるけれど、年や季節によってかなりの差があります。冬など野菜やその種類が少ない時期もあり、産消提携のように1年間のサイクルで買ってもらわないと、むずかしいです。」 「今日はこんなにたくさんのお野菜が入れられるけれど、年や季節によってかなりの差があります。冬など野菜やその種類が少ない時期もあり、産消提携のように1年間のサイクルで買ってもらわないと、むずかしいです。」
また、「今年はトマトがつぎつぎできているけれど、去年などは病気にかかって全く収穫できなかったのです。あちらこちらにトマトが出荷できないと連絡を入れるのが大変だった」そうで、そのあたりのこともわかったうえで買ってもらえる関係が大事だと教えてくださいました。有機で露地栽培をされているところでは、皆同じことをおっしゃいます。婦木さん自身、18年間有機栽培をしてこられたそうで、生産者と消費者の顔の見える関係をずっと続けておられるそうです。
 今度は、畑をみせていただきました。 今度は、畑をみせていただきました。
作業場の近くの畑では、ズッキーニが植わっていました。今年は雨が多く、ズッキーニが腐ってしまうそうです。
少し離れたところにある畑には車で行きました。なすやトマトの苗木が、元気よく立っています。苗木を支えるためにワイヤーが張ってありますが、その組み方が幾何学的でとても美しく、りりしく並んでいるのが印象的です。トマトがたくさん実り、今朝収穫したばかりというのに、もうつぎに収穫を待っている真っ赤なトマトがあちらにもこちらにもあります。
作業場では、婦木さんが奥様とお二人で、トマトを2kgづつ袋詰めにしておられました。「じつは、この秋に村を解放して、農村探検のようなことを考えています。実際に行なうについて、モニターのようなかたちで一度試してみようかと考えているのです。」とのお話。モニターなら旬菜どっとこむのメンバーが手を上げます!!よね。
いろいろお話をお聞きし、作業をお邪魔したうえに、出荷できないというトマトときゅうり、青豆の枝豆を分けていただきました。ありがとうございました。
[乳牛のおはなし]
 婦木さんちは、乳牛も9頭、飼っておられます。ここで搾乳された牛乳が氷上牛乳になります。皆、耳に番号札のピアスをして、飼葉や野菜を食べています。 婦木さんちは、乳牛も9頭、飼っておられます。ここで搾乳された牛乳が氷上牛乳になります。皆、耳に番号札のピアスをして、飼葉や野菜を食べています。
婦木さんのお父様にお話を伺いました。
「毎朝、搾られた乳はパイプを通って冷蔵タンクに集められ、5℃に保冷します。回収時には必ずサンプルを採り、9軒の生産者から集められた乳を混乳した後の検査で異常が出たときには、9軒各々のサンプルを検査し、どの生産者の乳が原因かを確定します。このような場合の牛乳は一切出荷できず、その損失は出荷した酪農家が処分費用も含めて負担します。」生産者の緊張感は、半端ではありません。
 「牛も人と同じで、いつも健康とは限りません。高温多湿になる梅雨の時期は、食欲が落ち、牛は体調を崩しやすく、病気にかかりやすくなります。どうしても投薬が必要な時は、搾られた乳は出荷できません。薬の成分が出ていないことを確認して、ようやく出荷できるのです。また、投薬など治療の記録はカルテに残ります。」牛も風邪を引くのです。 「牛も人と同じで、いつも健康とは限りません。高温多湿になる梅雨の時期は、食欲が落ち、牛は体調を崩しやすく、病気にかかりやすくなります。どうしても投薬が必要な時は、搾られた乳は出荷できません。薬の成分が出ていないことを確認して、ようやく出荷できるのです。また、投薬など治療の記録はカルテに残ります。」牛も風邪を引くのです。
「また、乳牛ならいつでも乳が出る、というわけではありません。乳を出すためには、子牛を産まなければなりません。そのために種付けをするのも大切な仕事です。また、生まれた子牛の世話も大変です。初乳は出荷できないので、それを保管して子牛にやり、なくなったら代用乳や野菜などで慣らしていきます。」本来、子牛が飲むはずの乳を、人間が頂戴しているわけです。
「アメリカではホルモン注射が日常的に行なわれていますが、ここでは使わないのですか。」とギデオンくんがたずねます。
「使いません。出産後60日から80日の間に種付けできると、一年中搾乳できるので、理想的ですが、なかなかそうはいきません。よほど発情に支障があるとき以外はホルモン剤の注射はしません。」ギデオンくんが驚いていました。
「1年のうち1ケ月半ほどは、北海道に行って放牧します。健康に気を使って世話をしています。」牛も旅をするのですね。
「全頭検査導入後、いろいろな情報を報告する必要があり大変だけれど、これでなにかあってもすぐに確認できるので安心です。」
その一方、安全の確保など生産者側に求められるものが多く、乳牛の世話を続けるひとがどんどん減ってきている現状があります。
「そのうち、国産では供給しきれず、海外から輸入する日も近いのでは」という不安なお話も聞きました。これからはもっと心して牛乳をいただきます。ありがとうございました。
[春日町、山秀猪肉店のはちみつ]
婦木さんの畑を後に、宇津江さんちに戻ります。
宇津江さんの奥様手づくりの黒豆入りちらし寿司をごちそうになり、キウイのシャーベットをいただきながら、はちみつの話になりました。
宇津江さんがキャラバンでいつも持ってきてくださる山秀猪肉店のはちみつには、いろんな種類があります。以前いただいたのは、両部という植物のはちみつです。
今回味見をさせていただいたのは、桜、樫、椎、ソヨゴです。食べ比べると確かに違いがわかります。はちみつの味比べなんて、初体験です。3種類をセットした贈答用のパッケージを作ったそうです。うーん、次回のキャラバンで持ってきていただこうかな。
旅の最後に、有機の町、市島町に足を伸ばしました。合鴨農法で稲作をしている畑が多いのでしょうか、あちらこちらに柵の張られた田んぼが見えました。以前、田植えに行った淡路島の五色町の合鴨さんは元気でしょうか。そんなことを考えながら、六甲アイランドへ帰ります。
<<文章:桃田 直子>>
▲ページTOPへ
レポート一覧へ戻る
|