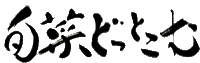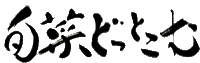|
合鴨水稲栽培研究会の田植えと「おかげ庵」訪問
【田植えお手伝い】
梅雨に入り、毎日が雨。そんななか、淡路へ田植えの手伝いにきませんか、というお声が旬菜どっとこむのメンバーに入りました。田植えの時期を迎え、加西市の北本さんや青垣町の宮井さんから田植えにどうぞ、とお声をかけていただきながら、日程がうまく調整できず、見送りになっていたところでした。ご縁というのは、こういうものなのでしょう。都合のつくメンバーで、かっとびけいこ号に乗っていざ淡路島へ。
明石海峡大橋を快調に走りぬけ、津名一宮インターを出て、海岸沿いを五色町に向かって走ります。目指す田んぼになんとかたどり着くと、すでに何組かのご家族連れが田んぼに入って田植えをしています。
五色町合鴨研究会は6年程前から活動をされており、田植えや収穫の時期にお手伝いいただく合鴨オーナー制度を取り入れているそうです。今回参加しているご家族のなかには4年前から毎年お手伝いにきているという方もおられました。ここで植えているのは、酒米の稲で、収穫後は、地元の酒造メーカーによってお酒になります。田植えなどお手伝いをした方々には、優先的に出来上がったお酒を購入していただけます、とうれしいお話。手伝う手にも力がはいるというものです。
お話を伺っていると、ピーピーと合鴨の泣き声が聞こえます。6月9日に入荷した、生まれて10日ほどの合鴨の雛が2羽運ばれてきました。黄色と黒のまだらの毛色に、短い羽。この合鴨が、田んぼの虫を食べてくれるのです。田植えが終わって数日もすれば、この合鴨たちが田んぼの番人(番鳥?)をしてくれるのです。よい酒米ができますように、くれぐれもよろしく。
田んぼの3分の2ほどに稲が植えられました。が、徐々に手伝う人数が減ってきています。今回は、見学のみで田植えはちょっと、と思っていた旬菜メンバーでしたが、そこは、やはり捨て置けない旬菜メンバー。いわおさんとはまださんがズボンをひざまで折りあげて、いざ、田んぼに入ります。
研究会のメンバーが、しるしのついた縄を向こうとこちらで持ち、縄を正面にして8人ほどが稲を手に並んでいます。自分の前にある縄のしるしを目当てに数本の稲を田んぼに植え付けます。途中、田植え歌なども歌いながら、結局、最後の最後までやり遂げました。お疲れ様です。
田植えが終わり、お昼の時間です。研究会メンバーの奥様たち手づくりのカレーが用意されていました。材料はもちろん、手塩にかけた合鴨と野菜、お米です。無農薬栽培のそら豆も食しました。
食事が終わると、参加者の自己紹介や研究会の1年の活動報告がありました。生産者と消費者の顔の見える関係をつくり、維持することは、多くの手間と様々な努力とが不可欠だということを、ここでも痛感しました。都会と農村が交流を深めることで、もっと助け合えることがあるのかもしれません。
【おかげ庵訪問】
いろいろな夢が、あちらこちらにあります。今回の田植え体験を紹介してくださった榎本さんは旬菜メンバーいわおさんのお知り合いの方ですが、この淡路にほれ込み、旧家を修復した庵を、「おかげ庵」と名づけ、都会と農村の交流の拠点にしたいと語られています。
その「おかげ庵」にお邪魔しました。江戸時代からの城下の武士のお住まいを、多くの人の協力で修復したもので、それはそれは趣のある建物です。ここには、鳥のさえずりを聞き、満天の星を眺め、田毎の月をめでる空間があります。都会の喧騒を忘れる、癒しの場になるでしょう。また、地元産の猪豚で生ハムをつくったり、地元でとれた小麦を使ったパンをつくったりできる工房をお庭に建てるのが夢とのことです。
さて、おみやげは淡路産のタマネギです。研究会の新家さんにお願いして、10kg2000円で分けてもらいました。やっぱり、おいしいおみやげがないとね。
田植え体験には、ウェルネスパーク五色にある五色温泉「ゆ〜ゆ〜ファイブ」の入浴券がついていました。ひとっぷろ浴びて、さあ、六甲アイランドへ帰りましょう!!
<<文章:桃田 直子>>
▲ページTOPへ
レポート一覧へ戻る
|