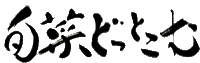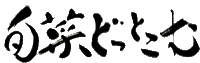|
新茶摘みと奈良茶飯に感激す
そば打ちに続く体験イベント第2弾!!我が旬菜メンバーは大いに張り切っていました。西名阪を「かっ飛びけいこ号」(岩尾さんの車です 笑)でひた走り2時間で葉香製茶の辰巳さん宅へ到着しました。
 毎週末には天気が崩れることも多かったのですが、メンバーの行いが良いせいか、どピーカンのよい天気。着いたのはちょうどお昼頃でしたが辰巳さんのご好意でまずはおいしいお茶とお菓子で一服させていただきました。 毎週末には天気が崩れることも多かったのですが、メンバーの行いが良いせいか、どピーカンのよい天気。着いたのはちょうどお昼頃でしたが辰巳さんのご好意でまずはおいしいお茶とお菓子で一服させていただきました。
 梅の花を砂糖漬けにしたものをお湯呑みに入れてお湯を注ぎ、砂糖が溶け、梅の香りを楽しみながら、梅の花が開くのをゆっくりと愉しむ飲み物など一つ一つが興味津々でした。ちなみにこの砂糖漬けは簡単にできるそうです。 梅の花を砂糖漬けにしたものをお湯呑みに入れてお湯を注ぎ、砂糖が溶け、梅の香りを楽しみながら、梅の花が開くのをゆっくりと愉しむ飲み物など一つ一つが興味津々でした。ちなみにこの砂糖漬けは簡単にできるそうです。

さて、ひと心地着いたところで早速製茶工場を見学させていただきました。
 うず高く積まれた茶葉をどんどんベルトコンベヤーに乗せていく少年。辰巳さんの末っ子の彼の働く姿の美しいこと、しかもよく働くのです。機械の行う作業や操作についてもきちんと説明してくれ、頼もしい働き手の一人であることは間違いないでしょう。 うず高く積まれた茶葉をどんどんベルトコンベヤーに乗せていく少年。辰巳さんの末っ子の彼の働く姿の美しいこと、しかもよく働くのです。機械の行う作業や操作についてもきちんと説明してくれ、頼もしい働き手の一人であることは間違いないでしょう。
製茶の手順を簡単に説明していきましょう。


まず、ベルトコンベヤーに乗せられた茶葉は蒸されます。ここが肝心なところで、焙番茶、煎茶や玉露といった等級が分かれるのはこの作業にかかってきます。蒸気をあてる時間や温度をその時の気温や湿度で微妙に調整しなくてはなりません。長年のカンがものをいうところです。
次に蒸された茶葉を冷ましてから乾燥させる機械に通します。これだけでは十分に水分が取れないので次に揉捻機という手で揉む作業をする機械にかけてじっくり水分を取っていくのです。そして最後は手作業で揉んで終了。一気にやればおいしいお茶にはなりません。一生懸命愛情を込めて作られたお茶が私たちの元へ届けられるのです。
見学が終わって、お楽しみのお昼です。奈良茶飯というご飯をいただきました。お米にほうじ茶としょうゆ、酒を適宜入れ、大豆を炒って入れて炊きます。炒った大豆とほうじ茶の効果が相まって実に香ばしいご飯のできあがりです。茶粥は食べたことがありますが、奈良茶飯は初めてでした。細かい分量は失念してしまったので後日調べて「ちょっとおいしい話」のコーナーでアップすることにします。そして大磯さんが卵焼き、岩尾さんがお漬物など、持ち寄ったおかずと奈良茶飯は最高に美味しかったことは言うまでもありません。
 腹ごしらえが済んだところで、最大の目的である茶摘の始まりです。お茶摘みの説明をお聞きし、お茶摘の機械を見せていただいた後、軍手につばの広い帽子をかぶっていざ!茶畑へ。 腹ごしらえが済んだところで、最大の目的である茶摘の始まりです。お茶摘みの説明をお聞きし、お茶摘の機械を見せていただいた後、軍手につばの広い帽子をかぶっていざ!茶畑へ。
今回、茶摘をしたのは有機栽培されている自家用のやぶきた種です。茶摘の方法はまず茶葉の先端部分てんぺんから2番目くらいの茶葉までをつまんでポキッと折ります。簡単に折れるところで折ります。無理やりへし折った場合はトウが立った部分まで折っているらしいです。若い部分はすぐに折れるそうです。
 茶葉がくるっとカーブしているものは若い葉です。そういった葉をなるべくたくさん入れながら摘んでいきます。有機栽培なのでくもの巣や青虫がいますがそれを上手に払いつつ進めて行きます。件の少年も手伝ってくれましたが手際の良いこと、あっと言う間にかご一杯に積んでいました。 茶葉がくるっとカーブしているものは若い葉です。そういった葉をなるべくたくさん入れながら摘んでいきます。有機栽培なのでくもの巣や青虫がいますがそれを上手に払いつつ進めて行きます。件の少年も手伝ってくれましたが手際の良いこと、あっと言う間にかご一杯に積んでいました。
私たちは慣れない作業でモタモタしつつもなんとか茶摘を終え、次はお茶にする作業が待っています。
 今回はホットプレートで釜炒り煎茶というのに挑戦してみました。これが曲者で、暑いわ、時間がかかるわの大変な作業でした。たくさん摘んだはよいけど、とても時間内にすべてを処理できません。そんなわけでホットプレートのある私や桃田さんは自宅で作業と相成りました。 今回はホットプレートで釜炒り煎茶というのに挑戦してみました。これが曲者で、暑いわ、時間がかかるわの大変な作業でした。たくさん摘んだはよいけど、とても時間内にすべてを処理できません。そんなわけでホットプレートのある私や桃田さんは自宅で作業と相成りました。
やり方ですがとても簡単。ホットプレートを中温で温めて摘んできた茶葉を入れます。じゅーというので一人は上手にお箸でほぐしながら、もう一人は軍手をはめて手揉みします。
だんだん茶葉が丸まって乾燥し、かさが減ります。からからになったら出来上がり。熱を加えても緑色が変色しないのに驚きました。葉が茶色になるのは紅茶やウーロン茶など発酵させた場合で空気に晒しておくのだそうです。1日外で晒して発酵させ、初めて紅茶やウーロン茶になるわけです。ちょっと意外な感じですね。
めいっぱい汗をかき、おいしいものに舌鼓をうち充実した時間を過ごさせてくださった辰巳さんに感謝したいと思います。
<<文章:鈴木 緑>>
▲ページTOPへ
レポート一覧へ戻る
|