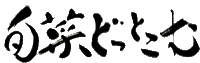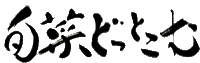|
産地訪問記〜岡さんちの畑
3月だというのに、六甲アイランドにも雪が舞い散るとっても寒い日。今日は、岡さんの畑にじゃがいもの植付けに行きます。しっかり着込んで、旬菜どっとこむフルメンバーは車に乗り込み出発です。途中、今日の後半で伺う予定の、春日町は宇津江さんのお宅に、携帯電話で雪の状況を確認。「よほど吹雪いているだろうな。」という皆の不安とは異なり、「晴れていますよ。道も大丈夫でしょう。」との、ちょっと心強いお言葉が返ってきました。
 岡さんちには順調に到着。畑がぬかるんでいるので、ゴム長靴に履き替えるようにということで、岡さんちの黒くて、頑丈そうな長靴をお借りして、いよいよ畑仕事に出かけます。私たちがじゃがいもを受け付ける畑は、以前たまねぎを植えたのと同じく、いつもおいしい卵を産んでくれる鶏たちの鶏舎の前にあります。以前に植え付けたたまねぎは20cmほど芽を伸ばし、雪の降る寒い畑でしっかり根付いていました。
岡さんちには順調に到着。畑がぬかるんでいるので、ゴム長靴に履き替えるようにということで、岡さんちの黒くて、頑丈そうな長靴をお借りして、いよいよ畑仕事に出かけます。私たちがじゃがいもを受け付ける畑は、以前たまねぎを植えたのと同じく、いつもおいしい卵を産んでくれる鶏たちの鶏舎の前にあります。以前に植え付けたたまねぎは20cmほど芽を伸ばし、雪の降る寒い畑でしっかり根付いていました。
  その隣の畝に、じゃがいもを植え付けます。植え付けるじゃがいもは、すでに岡さんが準備をしてくださっていました。芽がひとつ以上ついている3cmほどに切り分けられたじゃがいも片で、栄養液に漬けたものです。それを、畝に10cmほどの深さの穴を開け、芽が上になるように植えていきます。1本の畝の両端に15cmほどの間隔で植えていき、畝の中央部分には、EM菌の肥やしを入れていきます。「しっかり育ってね。」と声をかけながら、じゃがいも片に土をかぶせていき、今日の畑仕事は完了です。 その隣の畝に、じゃがいもを植え付けます。植え付けるじゃがいもは、すでに岡さんが準備をしてくださっていました。芽がひとつ以上ついている3cmほどに切り分けられたじゃがいも片で、栄養液に漬けたものです。それを、畝に10cmほどの深さの穴を開け、芽が上になるように植えていきます。1本の畝の両端に15cmほどの間隔で植えていき、畝の中央部分には、EM菌の肥やしを入れていきます。「しっかり育ってね。」と声をかけながら、じゃがいも片に土をかぶせていき、今日の畑仕事は完了です。
  隣の畝に育っていた水菜をしっかりおすそ分けしていただき、鶏たちにもご挨拶。いじめられっこの鶏が、ちょっとさみしそうに皆と別の場所にいました。鶏たちの餌の中身をみせていただき、産みたての卵を集めて、作業場に戻ります。 隣の畝に育っていた水菜をしっかりおすそ分けしていただき、鶏たちにもご挨拶。いじめられっこの鶏が、ちょっとさみしそうに皆と別の場所にいました。鶏たちの餌の中身をみせていただき、産みたての卵を集めて、作業場に戻ります。
途中の道端でつくしを見つけ、ヨモギを摘み、春の足音を見つけました。雪のちらちら舞うなか、寒さを忘れて自然の空気を味わいます。
さあて、次は横手さんの手打ちうどんを食べる番です。ちょこっと農業でお腹もちょうどすいてきました。2台の車に分乗して、いざ、出発。
 途中、岡さんの計らいで、いちご摘みのできるハウスに寄りました。 途中、岡さんの計らいで、いちご摘みのできるハウスに寄りました。
種類は「あきひめ」。
摘み取りやすい高さの棚にいちごが植え付けられ、液肥をパイプで送ります。元気に広がった葉の陰からきれいで大きないちごが数個づつぶら下がっています。真っ赤に色づいたものがおいしいとのことで、いく筋も並んだいちごの棚を行ったり来たり。持ち帰り用のプラスチック容器が、すぐに真っ赤ないちごでいっぱいになりました。お値段は2400円なり。食べるのが楽しみです。
 
【宇津江さんちで氷上牛乳のお話】
横手さんのお店を出て、卵を受け取りに岡さんの作業場に戻ります。卵と水菜、EM菌で育てた丸大根という、ほんとにまるまるした大根をおみやげにいただいて、岡さんご夫婦にお別れします。次の目的地、春日町に向かって出発です。
途中、吹雪の中を突っ走るという状況になり、豊岡育ちの大磯さんから山の天候の恐ろしさについて聞きました。なんとか天候が持ち直しますようにと祈る思いで先に進みます。
なんとか無事、春日町の宇津江さんのご自宅に到着です。婦木さんのお野菜や丹波の特産品を運んでくださる宇津江さんご夫妻には、いつもお世話になっています。今日は、氷上牛乳についてのお話を伺います。
宇津江さんには、前々回、六甲アイランドに来ていただいたときから氷上牛乳をお願いしています。以前メンバーの岩尾さんがお邪魔したときに、氷上牛乳には、お野菜でお世話になっている婦木さんの乳牛のお乳が使われている、というお話をお聞きしたことがきっかけです。
氷上牛乳は、氷上郡の約40件、朝来郡・養父郡の約30件の生産者から集めた牛乳が原料になって作られています。ここでは、飼料をできる限り自給をし、飼育現場もみることができるようになっています。牛乳は前日の夕方と、当日の朝搾乳された新鮮なもので製品化しているのが特徴で、なかでも、ノンホモライズという無調整の牛乳は、生産者限定9名で作り上げた牛乳です。そのお一人が婦木さんであり、今日は用事でお目にかかれなかった中野さんです。ぜひ、次回は牛たちにお目にかかりたいものです。
 宇津江さんが、味見をしてほしいということで、カップ入りのヨーグルトを2種類、用意してくださっていました。ひとつは、有機農業研究会の農業祭で見た覚えのある「たべちゃえ丹波」。もうひとつは「氷上ヨーグルト」です。皆で食べ比べながら、こちらがおいしいとか、甘くないもので小さいカップ入りがほしいとか、しっかりモニターさんです。「次回、六甲アイランドにおいでのときには、ぜひヨーグルトもお願いします。」と、食べることには貪欲な旬菜メンバーでした。 宇津江さんが、味見をしてほしいということで、カップ入りのヨーグルトを2種類、用意してくださっていました。ひとつは、有機農業研究会の農業祭で見た覚えのある「たべちゃえ丹波」。もうひとつは「氷上ヨーグルト」です。皆で食べ比べながら、こちらがおいしいとか、甘くないもので小さいカップ入りがほしいとか、しっかりモニターさんです。「次回、六甲アイランドにおいでのときには、ぜひヨーグルトもお願いします。」と、食べることには貪欲な旬菜メンバーでした。
宇津江さんちの庭先にある大きなコンテナのなかには、お米など温度管理の必要なものが保管されています。コンテナの外側には、きのこがたくさんついた木が何本も立てかけてあります。裏手には、山からの清水が流れてきています。雪がちらつく冷たい空気が、とってもおいしく感じられました。
【宮井さんの大根畑】
宇津江さんの車の先導で、今度はもっと山奥の青垣町の畑に向かいます。雪はちらちらするものの、どうやら道路の状態に問題はなさそうです。
青垣町の宮井さんの畑は、山に向かって進む道の一番奥にあるという感じです。杉の森をすぐ背にして、気温も何度か低くなっています。自然農法で稲や大根などを作っておられる宮井さんは、新大阪にお住まいです。週末ここ来られて、農業をしているそうです。この日は仲間の方が来ておられました。尼崎で溶接工の仕事をしておられる築山さん、青垣町で陶芸をされている藤井さんです。
 畑で凍った大根を見て回りました。何本か抜いてみました。畑の脇の作業場で暖をとりながら、自然農法や、野菜作りをはじめた動機などをお聞きしました。 畑で凍った大根を見て回りました。何本か抜いてみました。畑の脇の作業場で暖をとりながら、自然農法や、野菜作りをはじめた動機などをお聞きしました。
土や水、おてんとさまのお手伝いをしているだけです、というお言葉が出てきました。土の中の微生物を活性化させることが肝心で、そのためになにをするか、自然の力に寄り添ってするそうです。また、種を蒔く時期の大切さも教えていただきました。この時期が一週間でもずれると、収量が異なり、収穫の時期が1ヶ月は、ずれ込んでしまうとのことです。
大根は、8月最終週に種をまき、2年かけて育ちます。すすきを刈ったものを肥料にしたり、雑草を押さえるために畑にのせておくそうです。
 メンバーの岩尾さんが、以前この畑にきたとき、下のほうがぷっくりした、しもぶくれ大根(旬菜メンバーはこう呼んでいます)を土から抜くのがとっても大変だった、とお話したところ、その大根は本体と同じくらいの長さの根が土の中に張っているため、とても抜きにくい大根だということでした。今年は、土を少し高く盛って植えてみようと思っているとのことでした。 メンバーの岩尾さんが、以前この畑にきたとき、下のほうがぷっくりした、しもぶくれ大根(旬菜メンバーはこう呼んでいます)を土から抜くのがとっても大変だった、とお話したところ、その大根は本体と同じくらいの長さの根が土の中に張っているため、とても抜きにくい大根だということでした。今年は、土を少し高く盛って植えてみようと思っているとのことでした。
自然を相手にしていると欲をかいたらいけないそうです。腹を立ててはいけないそうです。自分がそのような心持ちになると、うまく育たないのだそうです。生きているものをいただくという心や、失敗しても感謝すること、愛情をいっぱいかけてやることが大事なのだそうです。
岡さんの畑、横手さんの手打ちうどん、宇津江さんと丹波の特産品、宮井さんの大根。こだわりを持って自分の道を生きる人たちには、瞳の奥に輝くものがあります。そこから生み出されるものには、命が吹き込まれています。それを、少しおすそ分けしていただいて、旬菜どっとこむのメンバーは、こころの潤いをいただきます。
雪もおさまり、夕暮れせまる景色の中、今回もこころにいっぱいのおみやげを詰めて、車は六甲アイランドへと向け走ります。
<<文章:桃田 直子>>
▲ページTOPへ
レポート一覧へ戻る
|