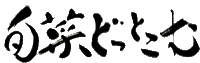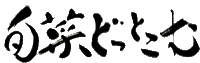|
北本さんちでそば打ち体験
新年早々、厳しい寒さの続いていた中、ぽっかりと小春日和となった12日。昨年末より計画の、北本さんが育て収穫されたそばの実を使ったそば打ち体験に挑戦する日です。
北本さんちに到着すると、そこには、すでに一番粉、二番粉、三番粉と書かれたそば粉が用意されていました。また、そば打ちをしたあとで、そばの実を粉にする工程も体験できるようにと、石臼やふるいも用意してくださっていました。
そのうえ、北本さんの畑で収穫されたばかりの水菜を使ったなべも準備され、皆で乾杯するための切り立ての竹製おちょこを用意すべく、北本さんのご近所の方たちが竹林に行っているとのお話です。盛りだくさんのメニューに心が弾みます。
竹製おちょこを待つ間に、そば打ちの道具を準備し、お湯を沸かしながら、北本さんにはそばの実が粉になるまでの苦労を教えていただきました。なかでも、そばの実を石臼で挽いたあと、そば殻とそばの実を分ける作業の細かく大変だったことには驚きました。今回は、北本さんのご近所さんがピンセットを使って夜なべ仕事で分けてくださったそうです。
ふるいにかける作業もなかなかのものです。粉が部屋中に飛び散って、そこらじゅうがそば粉だらけだったそうです。とくに一番粉になると、もっとも目の細かいふるいにかけるので、ふるいの目がすぐに詰ってしまい、なかなかふるえないとのことでした。
こんなに手間隙かけてそば粉になっているのだと思うと、そば粉を大事に扱わなければいけないと思うとともに、それを食べることへの有り難味がいっそう深まります。
竹製おちょこが届くあいだに、草野先生にはそばがきのつくり方をご指導いただき、三番粉の味見をしました。そばの色、香り、味と、まさに視覚、臭覚、味覚で味わいました。
 総勢15~6名が揃ったところで、水菜とうすあげのおなべを囲み、竹製おちょこで乾杯。いまからこんなにいい気分でそば打ちができるのかな、という、たのしげな不安を持ちながら、これも何かのご縁という出会いに、皆酔いしれました。 総勢15~6名が揃ったところで、水菜とうすあげのおなべを囲み、竹製おちょこで乾杯。いまからこんなにいい気分でそば打ちができるのかな、という、たのしげな不安を持ちながら、これも何かのご縁という出会いに、皆酔いしれました。
さあ、お酒も入ってみんな元気いっぱい、絶好調になったところで、いよいよそば打ちです。師匠の草野先生は白衣に白い帽子をかぶり、まさに実習授業のはじまりです。
 先生の実演は、10割そばの挑戦ではじまりました。そば粉に水を入れ、さばきます。この水の量が勝負を左右するそうです。そのときのそばの水分含量や湿度、温度によって調整しなければならないとのことです。粉全体に水分がいきわたるよう、手早くさばき、そうこうしているうちに徐々にそばがまとまってきます。この工程をみていても、そば打ちは、力と体力、それに根気が必要だと感じます。 先生の実演は、10割そばの挑戦ではじまりました。そば粉に水を入れ、さばきます。この水の量が勝負を左右するそうです。そのときのそばの水分含量や湿度、温度によって調整しなければならないとのことです。粉全体に水分がいきわたるよう、手早くさばき、そうこうしているうちに徐々にそばがまとまってきます。この工程をみていても、そば打ちは、力と体力、それに根気が必要だと感じます。
さすが師匠。そば粉はうまくまとまりました。
丸くまとめたそば粉を、長い麺棒を使って、均等に薄く、延ばしていきます。このとき、10割のそば粉では、先端部分にびび割れが入り易く、なかなか丸く広がりません。師匠の手際のよさが光ります。
伸ばし終わったら、折りたたんで、おおきな包丁で切っていきます。茹で上がると太くなるので、細くそろえてきることが必要です。ひとつひとつの工程に神経が注がれます。
 そばをゆでるのも、タイミングが大事です。茹で上がったそばを冷水で洗うことも、気が抜けません。 そばをゆでるのも、タイミングが大事です。茹で上がったそばを冷水で洗うことも、気が抜けません。
かくして茹で上がったそばを味見するころには、みんな同窓生のようです。
 いよいよ、これまでの工程を見ていた生徒たち(?)の挑戦がはじまります。10割のそば粉に果敢に挑む人。春日町のやまのいもを練り込んでつくる人。卵を練り込んで打つ人。一番粉、二番粉、三番粉といろんな粉で試します。 いよいよ、これまでの工程を見ていた生徒たち(?)の挑戦がはじまります。10割のそば粉に果敢に挑む人。春日町のやまのいもを練り込んでつくる人。卵を練り込んで打つ人。一番粉、二番粉、三番粉といろんな粉で試します。
「これは、だれが打った何割そばだ」だとか、「これはそばの色が違うけれど、どうしてか」、「歯ごたえや味がそれぞれ違っておもしろい」、「打つ人によって味わいが違う」など、次々に茹で上がるそばを味わいながら、うんちくがあちらこちらで聞かれました。
さらに、そばを延ばすときにできた、ひびわれた端っこが、これまた大のご馳走になります。熱した油で揚げたら、なんとそばチップス。茹でたそば以上においしいのでは、という言葉がでたほど、ビールのお友として、みなさんに大受けでした。
 そばづくしでお腹がいっぱいになったところで、少々力仕事をしてみますか、ということで、北本さんがそばを石臼でひく作業を試させてくださいました。 そばづくしでお腹がいっぱいになったところで、少々力仕事をしてみますか、ということで、北本さんがそばを石臼でひく作業を試させてくださいました。
はじめに、そばの実の汚れをとるために、大きなバケツにそばの実を入れて、壁土を撹拌する装置を使ってかき混ぜます。そうして、おおまかな汚れを取ったあと、そばの実に紛れて石ころが混ざっていないか一粒一粒目で見てチェックをします。その次に石臼です。
石臼のうえにある穴に少しずつそばの実を入れていきます。ごろごろと重い石の擦れる音を聞きながら、力をこめてそばを挽きます。こうして出てきたそばの粉も、まだすぐ食べられるものではありません。何度も繰り返し挽いて、そして何度も振るってようやくそば粉になるのです。
かくして、今日のそば打ち体験のメニューはすべて終了。最後は、コーヒーと紅茶をいただきながら、みなさんで過ごした旬の時間をゆっくり味わいます。
いつものように日が落ちかかったころ、これまたいつものように北本さんの畑でできたお野菜をいっぱい車に積み込んで、そしてなにより、こころとおなかがいっぱいになった旬の人たちを乗せて帰途につきました。
そば打ちの師匠、草野先生より、「そば麺のおいしさ」についてメールをいただきました。
それによると、
① そば粉が新鮮(新そばで引き立て)であること
② 加える水がおいしいこと
③ 打ったらすぐに茹でること
④ 茹では、たっぷりの熱湯内で短時間に仕上げること
⑤ 茹で上がったら、すぐに冷水でもみ、ぬめりが取れていること
⑥ 適当なそばつゆが用意されていること
⑦ そばつゆ作りにはコンブや鰹節など吟味される場合もあるが、醤油にワサビもしくはショウガが加わったものだけで十分味わいがあること
⑧ 食べる時点で空腹であること
⑨ 食べる場の雰囲気が親和的、友好的であること
⑩ そばはおいしいものだ、との観念を抱くこと
⑪ 食する人が心身的に健康であること
まだ、ほかにもあるかとは思われますが、・・・
今回の北本さんちのそば打ちは、このすべてが満たされていて、そのためとても「おいしく」いただけたんだろうと思います。(草野先生)
そばの実を真ん中において、いろんな人たちが集い、いろんな知識が広がり、こころが豊かになります。これからも、こんな経験をひとつづつ、ゆっくり重ねていきましょう。
<<文章:桃田 直子>>
▲ページTOPへ
レポート一覧へ戻る
|