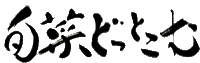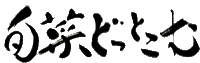|
産地見学会
【葉香製茶編】
 奈良県月ヶ瀬村というと私たちの住む兵庫県からはずいぶん遠い印象があるのだが、思いのほか早く到着したのだった。 奈良県月ヶ瀬村というと私たちの住む兵庫県からはずいぶん遠い印象があるのだが、思いのほか早く到着したのだった。
もちろん家までは標識もないこともあって葉香製茶の辰巳洋子さんが迎えに来てくださった。
その案内がなければとても迷わずには着かないだろうと思える道をこれでもかと私たちを乗せた車が登っていく。
 どこまで行くんだろうか?と思っていると茶畑が姿を現した。洋子さんに畑の中を案内してもらう。 どこまで行くんだろうか?と思っていると茶畑が姿を現した。洋子さんに畑の中を案内してもらう。
なんでも20年も前から有機栽培をされているということだった。確かに畑の地面はふかふかしてとても歩きやすく肥えているのが靴を通してもわかるくらいだった。
茶畑の地面にはマルチ代わりにわらが敷きつめてあり、それが畑の端で芽吹き、稲になっているところもあって驚いてしまった。他にもプチトマトやゴーヤ、枝豆など茶畑の空いたところに作物がすくすくと育っていてちょっとした家庭菜園状態だった。肥えた土地ではさすがに育ち具合が違う。
 雨が降ってきたので辰巳さんのお宅でお茶を飲みながらいろいろお話をした。辰巳さんは消費者に向けて「お茶っぱ」というミニ通信を発行して情報発信されていて、それが1冊の本になるくらいにまでなっていた。そこに20年の歴史を感じた。 雨が降ってきたので辰巳さんのお宅でお茶を飲みながらいろいろお話をした。辰巳さんは消費者に向けて「お茶っぱ」というミニ通信を発行して情報発信されていて、それが1冊の本になるくらいにまでなっていた。そこに20年の歴史を感じた。
継続は力なり・・・辰巳さんの熱意に脱帽である。
このときに煎茶、上煎茶、かぶせ茶、ほうじ茶などを試飲させていただいた。香ばしいほうじ茶、かぶせ茶や上煎茶の香りとコクいずれもおいしく、お茶好きな私としては大感激であった。
辰巳さんの「お茶も農作物なので味は毎年同じではない。おいしいときもあるしそうでないときもある。」というお話を聞いてまるでワインの当たり年みたいなものなのだろうかと思ってしまった。
【谷農園編】
 谷農園の小倉さんとはパタゴニアのスピーカーシリーズで出会ったのがきっかけだった。話は聞いていたがどんなところだろう。期待に胸がふくらむ。 谷農園の小倉さんとはパタゴニアのスピーカーシリーズで出会ったのがきっかけだった。話は聞いていたがどんなところだろう。期待に胸がふくらむ。
農家に行くのは大変である。目印もない、もちろん看板もない。地元の方の案内なしにはたどり着けないのである。小倉さんの車の先導で区画された田園風景の中を走り、鶏舎に到着。ここは谷農園と協働されている方の鶏舎です。あいさつもそこそこに早速鶏舎の中に入らせていただいた。


この鶏舎のオス、メスの比率は1:10、数は失念したがかなりの数が平飼いといって放し飼いで飼育されていた。私たちが訪ねたときも産みたてのほかほか卵が巣箱のなかにあった。どこの鶏舎に行っても、雌鳥が卵を産むのは狭くて薄暗い巣箱の中。やはり落ち着くのであろう。
小倉さん曰く、鶏舎の理想密度は1坪に10羽だそうだ。なかなか理想に近づくのは難しいらしく合理化をして卵は1個32円で販売しているそうだ。卵の価格の違いは飼料の自給率の違いであり、これがコストに5〜10倍となって跳ね返ってくる。彼はコストを下げるために餌用に畑を4反も使っている。その畑の野菜すなわち鶏の餌というわけだ。
循環
そして鶏肉は2年たつと肉が固くなり肉としての価値が下がるそうだ。となると卵をたくさん産み続けてもらうのか肉として販売するのか、まさに「卵を取るか、肉を取るか」の世界である。自然や動物相手の不安定な状況の中で生活していく大変さを垣間見たような気がする。
合理化といえばこんな話も聞いた。トウが立った野菜などは飼っている白鳥や鶏たちのエサになるのだそうだ。この白鳥と言うのは競馬場の池に放す白鳥を商品として出しているそうだ。徹底して低コスト化された運営に脱帽である。
 次にエゴマの畑を案内していただいた。エゴマの畑は15町だ。現代っ子の私には広さがぴんとこない。これらのエゴマは有機栽培されている、広さを考えるとその草取りなど手入れにかかるご苦労は計り知れないものだ。ちなみにエゴマ1キロで300CCのエゴマ油が取れる。エゴマの実など重さがあって無きがごとくなのでいかに大量の実が必要か理解いただけるかと思う。
次にエゴマの畑を案内していただいた。エゴマの畑は15町だ。現代っ子の私には広さがぴんとこない。これらのエゴマは有機栽培されている、広さを考えるとその草取りなど手入れにかかるご苦労は計り知れないものだ。ちなみにエゴマ1キロで300CCのエゴマ油が取れる。エゴマの実など重さがあって無きがごとくなのでいかに大量の実が必要か理解いただけるかと思う。
 エゴマは韓国でよく使われている食材でエゴマの実を絞ってエゴマ油にして炒め物に使ったり、実をご飯にのせて食べたりするそうだ。小倉さんのところではエゴマ油の絞りかすを丸めてエゴマクッキーにして販売している。そしてその作業は障害者の作業所で行っているそうだ。ちなみに私たちも試食用にエゴマ油を買ってみた。炒め物に使った感想だが
、さっぱりした感じで炒め物も脂ぎらなくてよいと思う。最初にシソ系の臭いがきついので炒め物にはどうかと思ったが熱すると案外気にならない。エゴマ油の瓶のそこには酸化防止のために大豆が入れられていて、人工的なものが用いられていないことに好感が持てる。 エゴマは韓国でよく使われている食材でエゴマの実を絞ってエゴマ油にして炒め物に使ったり、実をご飯にのせて食べたりするそうだ。小倉さんのところではエゴマ油の絞りかすを丸めてエゴマクッキーにして販売している。そしてその作業は障害者の作業所で行っているそうだ。ちなみに私たちも試食用にエゴマ油を買ってみた。炒め物に使った感想だが
、さっぱりした感じで炒め物も脂ぎらなくてよいと思う。最初にシソ系の臭いがきついので炒め物にはどうかと思ったが熱すると案外気にならない。エゴマ油の瓶のそこには酸化防止のために大豆が入れられていて、人工的なものが用いられていないことに好感が持てる。
 次に野菜畑を案内してもらう。ここでも肥料代わりにトウの立った野菜を畝の横に肥料として置く、冬の野菜不足に備えて漬物用として大根と高菜を植えるなど良く考えられた計画がなされていた。ただ好きなものを植えるというのでは家庭菜園レベルなので、農業一本で食べていくためにはこれぐらい頭を使って計画はしないと、ということだった。 次に野菜畑を案内してもらう。ここでも肥料代わりにトウの立った野菜を畝の横に肥料として置く、冬の野菜不足に備えて漬物用として大根と高菜を植えるなど良く考えられた計画がなされていた。ただ好きなものを植えるというのでは家庭菜園レベルなので、農業一本で食べていくためにはこれぐらい頭を使って計画はしないと、ということだった。
 とにかく自然相手で不確定要素が強い仕事ではあるけど、それがまた楽しく、知恵を絞って自然相手に稼がせてもらうという小倉さんの前向きな姿勢、農業にかける熱さを感じる。
とにかく自然相手で不確定要素が強い仕事ではあるけど、それがまた楽しく、知恵を絞って自然相手に稼がせてもらうという小倉さんの前向きな姿勢、農業にかける熱さを感じる。
 さて野菜畑は驚きの宝庫だった。オクラがこんな風に実っているとは。そして落花生の実り方のなんと不思議なことか。農業から離れた生活をしているので1つ1つに驚きがあった。そのほかにもいろいろ作物をみせていただいたが特に強く記憶に残ったのが上の野菜の姿だった。 さて野菜畑は驚きの宝庫だった。オクラがこんな風に実っているとは。そして落花生の実り方のなんと不思議なことか。農業から離れた生活をしているので1つ1つに驚きがあった。そのほかにもいろいろ作物をみせていただいたが特に強く記憶に残ったのが上の野菜の姿だった。
  最後は出荷場を見学させていただく。ビニールハウスの中では苗を育てたりしているようだ。また街まで自前のトラックで出荷するということもされていて立派なトラックが止めてあった。これに大量の農産物や卵を積んで共同購入グループや取引のあるスーパーなどに出荷しているのだそうだ。 最後は出荷場を見学させていただく。ビニールハウスの中では苗を育てたりしているようだ。また街まで自前のトラックで出荷するということもされていて立派なトラックが止めてあった。これに大量の農産物や卵を積んで共同購入グループや取引のあるスーパーなどに出荷しているのだそうだ。
小倉さんの将来の計画としては、現在稼動している就農したい人向けの研修場の他に農業体験をする子供たちの遊び場兼キャンプ場、障害者の就業施設として作業所を作り、みんなが楽しく生活できるようにすることが理想なのだそうだ。今までいろいろな農家の方に出会ったきたが、合理的な経営センスがありかつ楽しんで農業されている方も珍しいなと思う。
【農事組合法人しんせん農産編】
 さて最後は濱田さんのご紹介でお訪ねする「しんせん農産」さん。農場長の鈴木計さんに農園をご案内いただいた。 さて最後は濱田さんのご紹介でお訪ねする「しんせん農産」さん。農場長の鈴木計さんに農園をご案内いただいた。
 まずはうわさの空心菜の畑へ。空心菜は血をキレイにする作用があるだとかで最近脚光を浴びている野菜です。読んで字のごとく茎の中心が空洞で断面を切ったらまるでストローのような感じで不思議な形だ。初めて自分の目で見て驚いた。鈴木さんのご好意もあって少し収穫させていただく。 まずはうわさの空心菜の畑へ。空心菜は血をキレイにする作用があるだとかで最近脚光を浴びている野菜です。読んで字のごとく茎の中心が空洞で断面を切ったらまるでストローのような感じで不思議な形だ。初めて自分の目で見て驚いた。鈴木さんのご好意もあって少し収穫させていただく。
次にかぼちゃなどいろいろな野菜を植えた畑を次々にご案内いただく。下の写真はそれぞれの畑の様子だ。黄色の花が咲いているのはかぼちゃだそうだ。左の写真はレタスだろうか。
   

 野菜の中には虫がつきやすい品種もあり、左の写真のように防虫対策している。 野菜の中には虫がつきやすい品種もあり、左の写真のように防虫対策している。
 草が生えにくいようにマルシシートを使っている。農薬を使わないでとなるといろいろ防御策に手間がかかる。
草が生えにくいようにマルシシートを使っている。農薬を使わないでとなるといろいろ防御策に手間がかかる。
鈴木さんは脱サラをされてここで農業をされおられる。慣れない農作業にご苦労があったかと思われます。
周辺の田園風景はひなびた感じで散歩するのに最高 だった。
 
しんせん農産さんを訪ねた後、うわさの「もくもくファーム」に寄った。すでに16時を過ぎていたので野菜市を見学はできなかったが、おいしいご飯を味わい、付近を散策して短い時間だが堪能できました。
今回は兵庫県外へ初めて飛び出し、たくさんの驚き、発見があった。みなさんそれぞれ工夫をされて農業を営まれ、その努力に脱帽した。
<<文章:鈴木 緑>>
谷農園 小倉 和久さん
〒518-1147 三重県上野市蕨縄手160-6 TEL.0595-39-0005
農事組合法人 しんせん農産 鈴木 計
*2003年10月1日名称を「自然農法ひまわり」と変更。
〒518-0873 三重県上野市丸の内33-5
TEL./FAX.0595-24-9432
農場直通TEL 090-1757-0512
Emailhimawari@po2s.wisnet.ne.jp
URL http://himawari.wisnet.ne.jp/
▲ページTOPへ
レポート一覧へ戻る
|